こんにちは!ひだまり歯科です!
高齢になると、骨を丈夫に保つために骨粗しょう症のお薬を服用されている方が多くなります。
60歳代では5人に1人、70歳代では3人に1人、80歳代では2人に1人が骨粗しょう症を持っていると言われています。
そのため、訪問歯科を受けている方の多くも、何らかのお薬を服用していることが多いです。
これらの骨を強くするお薬のうち、『ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)』や『デノスマブ(RANKL抗体製剤)』などは、稀に「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)」という副作用を起こすことがあります。
これは、あごの骨の一部が炎症を起こして治りにくくなり、場合によっては骨が露出してしまう病気です。
この症状は、抜歯などの外科的な処置や、歯ぐきの感染(歯周病・根の病気など)をきっかけに起こることがあります。
そのため、感染の原因となる歯がある場合には、早めの治療や抜歯が必要となることがあります。
特に、骨粗しょう症の治療を始める前であれば、予後が非常に悪いであろう歯を抜いておくことやクリーニングや歯科治療を行うことで、後々のリスクを減らすことができます。
お薬を服用中の方も、定期的に歯科でお口の中をチェックし、清潔を保つことがとても大切です。
また、糖尿病やがん治療、ステロイドを使用している方は感染が起こりやすく、MRONJのリスクも高まるため、より丁寧な口腔ケアが必要になります。
以前は「抜歯のときには一時的に薬を中止したほうがよい」と言われていましたが、最新の指針(2023年版)では、原則として薬を止めずに抜歯を行うことになっています。
しかし、飲んでいるお薬との兼ね合いや体調等によっては休薬期間を設けたり、休薬まではせずとも骨粗鬆症のお薬の使用間隔にあわせて歯科治療治療するなど調整が必要な場合もあります。
主治医と歯科医が連携し、体調や服薬状況に応じて安全に治療を進めます。
骨粗しょう症のお薬を飲んでいる方は、痛みや腫れがなくても、定期的な歯科管理を受けることが重要です。
「入れ歯が当たる」「歯ぐきが腫れた」「少し痛む」といった小さなサインも、早めに歯科受診をしましょう。
日ごろのケアと連携が、あごの骨とお口の健康を守ります。
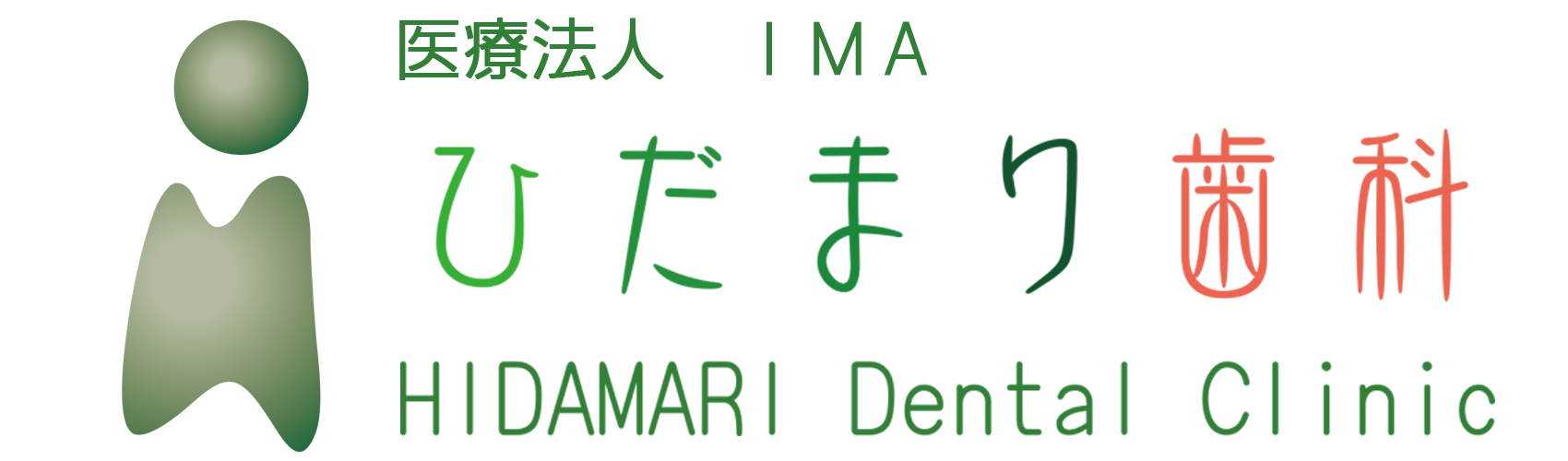

最近のコメント